 あ行
あ行 男帯の種類について サイズや素材/男性の兵児帯と角帯を解説(着物用語)
男帯の種類とサイズや素材についてまとめています。男性の帯は兵児帯と角帯の二種類で、それぞれを解説しています。(着物用語)
 あ行
あ行  あ行
あ行  あ行
あ行 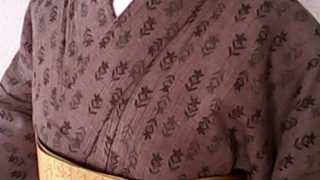 あ行
あ行  あ行
あ行  あ行
あ行  あ行
あ行  あ行
あ行  あ行
あ行  あ行
あ行  あ行
あ行  あ行
あ行  あ行
あ行