
◆縮緬生地と水引き
縮緬とは、生地の表面に「シボ」と呼ばれる凹凸(おうとつ)のある生地をいいます。
つまりツルんとしていない生地です。
生地の凹凸は、糸をあらかじめねじっておくことで作ります。
縮緬は光沢と独特の手触りを持ち、その生地は和装に多用されています。
ここでは着物の縮緬の生地について、シボができる仕組みや種類を説明します。
縮緬という生地ができる仕組み

◆縮緬生地の着物
布の生地は、経糸(たて糸)と緯糸(よこ糸)を交互に織り込むことでできあがります。
縮緬の生地をつくるときは、緯糸に強くねじった糸を用いることで、「シボ」とよばれる凸凹が生みだします。
糸をねじることを撚(よ)りをかけるといい、
縮緬の布を作るには、右に撚った糸と左に撚った糸を交互に織り込んでいきます。
縮緬のシボとは?
右に撚った糸と左に撚った糸を交互に織り込んでいき、布が織りあがったとします。
その後、暖かいお湯の中で糊を落とすと、
糸の撚りが戻ろうとする力が発生します。
右撚りの糸は左に、左撚りの糸は右に戻ろうとして分かれることで、
布の表面にデコボコができ、それが「シボ」とよばれるものです。
縮緬の種類

◆縮緬 着物の生地
このねじった緯糸の組み合わせによって、
風合の異なる縮緬生地が生まれます。
代表的なちりめんとして以下があります。
- 一越ちりめん
- 二越ちりめん
- 古代ちりめん
- 紋綸子ちりめん
- 紋意匠ちりめん
- 駒綸子ちりめん
- 鬼しぼちりめん
絹の白い縮緬の生地ができてから、色を染めていきます。
白い縮緬生地を染めて着物の反物に
縮緬の生地は、友禅染めや型染め、絞り染めなどの染めの着物に用いられます。
染める前の白い縮緬の生地は、
- 滋賀県長浜市
- 京都の丹後地方
で主に生産されています。
長浜市では、浜縮緬と呼ばれる模様のない白生地が生産されており、
丹後地方では、無地縮緬と紋縮緬が織られています。
縮緬の歴史・始まりは

◆縮緬 着物の生地
縮緬(ちりめん)は、日本の伝統的な織物で、その特徴は今お話ししたような独特のしわ加工にあります。
縮緬の歴史はかなり古く、起源については諸説ありますが、一般的に以下のように説明されています。
1. 時期
縮緬が最初に織られ始めたのは、平安時代(794年 – 1185年)から鎌倉時代(1185年 – 1333年)にかけてとされています。
しかし、縮緬特有の加工技術が発展したのは江戸時代(1603年 – 1868年)に入ってからです。
2. 起源
正確な起源は不明ですが、古代の中国や朝鮮半島から伝わった織物技術が日本で独自の進化を遂げたとされています。
3.発展
江戸時代に入ると、技術の進歩や商業の発展により、縮緬の生産が拡大しました。
特に、京都が縮緬生産の中心地となり、高度な技術を持つ職人たちによってさまざまな種類の縮緬が生み出されるようになりました。
江戸時代の中期には、丹後に住んでいた絹屋佐平治さんが、京都で勉強した技を持ち帰ったのが丹後地方での発展の始まりとされています。
縮緬は、着物や帯、小物などに使われ、日本の伝統文化や工芸技術の美を象徴する素材として今日も高く評価されています。
縮緬 ちりめんとは/布 シボって何? 種類を着物の生地で説明(着物用語)まとめ
縮緬のシボは緯糸のねじり方によって、でき方が違い、種類も変わります。
シボがわかりにくいときは、ツルツルした着物と糸の状態を見比べてみてください。
慣れるとすぐに見分けがつくようになります。
縮緬の生地はよりをかけてあるため、多くの糸が必要になります。
そのためツルツルした生地の着物より重く、水洗いすると縮みやすいので注意してください。
<関連ページ紹介>
◆紬の着物とはどんなきもの?

◆色無地の着物はいつ着る?特徴や合う帯
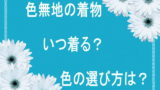
◆千鳥柄とは・意味・着物の季節はいつ?






コメント