
着物の虫干しの季節はいつですか?
部屋が狭いので、簡単にできる方法について知りたいです。
そんなご質問に詳しくお応えします。
「虫干し」というのは着物の湿気をとばし、乾燥した空気を通すことが目的です。
ですから湿度の低い乾燥した季節に行います。
虫干しに適した季節や時期、時間、やり方詳しくお話しますね。
着物の虫干しの季節・時期
乾燥した季節でおすすめの時期
着物の虫干しに最もおすすめな季節は空気の乾燥した季節で、
- 7月下旬から8月上旬:土用干し
- 9月下旬から10月中旬:虫干し
- 1月下旬から2月上旬:寒干し
がおすすめです。
それぞれ「土用干し」「虫干し」「寒干し」といわれてきました。
いずれも晴天が2日以上続いた次の日が、地面も空気も最も乾き湿度が低くなります。
晴天が数日以上続けば、上記にない3月や5月でもよいでしょう。
虫干しの回数は何回?
一年に2回ないし3回虫干しをするのが理想ですが、そんなに頻繁に行うのが難しい場合は、年1回でも行ってください。
虫干ししないと起きる着物のトラブル
虫干しをせずに長期間保管すると起こりやすいトラブルをあげてみます。
- カビの発生
- 色あせ
- 変色
がトラブルの主なものです。
中でも湿気が原因のカビのトラブルが最も多いです。
カビはその着物だけでなく、タンスの中で広がりやすいので虫干しの際にチェックしてみましょう。
現代の住宅事情ではサッシの窓が普及し、気密性が高くなりがちです。
部屋だけでなく着物が入ったタンスの中も湿度が高くなりやすい環境にあります。
カビの発生に適した環境(温度と湿度)
カビは室温20~30℃くらい、湿度が60~85%で発生しやすいです。
私たちが快適だと感じる湿度は50~60%くらいです。
東京なら1~3月に湿度が50~60%となり、最も低い季節です。
北陸地方では、1年を通して70台前半から 80台前半の湿度があります。
比較的湿度が低いのが3月4月5月。
なのでこの時期に虫干しを行うのが良いでしょう。
湿度計があれば60%を切るのを目安に。
効果のある虫干しの方法
虫干しの時間と具体的な方法
虫干しは着物の湿気をとるのが目的ですが、日光にあてないことも大切です。
日光にあてると、そこだけ色があせることがあるからです。
また湿度が高くなる時間まで干すのはよくありません。
虫干しの方法をまとめると、
- 正午をはさんで2~5時間
- 直射日光にあてない
- 蛍光灯にあてない
- 風通しのよいところで
- 15時を目安にしまう
以上の点を守っていただくと、最も効果的に虫干しができます。
マンションの場合の湿気対策
マンションにお住まいで窓を開けにくい、湿度がさがりにくいという方は、
- 扇風機をつけて着物に風を通す
- エアコンをつけて湿度をさげる
という方法もあります。
最もおすすめな虫干し方法

◆訪問着を着物ハンガーにかけて
虫干しするとき、理想的なのは、
- 着物は着物ハンガーに一枚づつ
- 帯もハンガーに一枚づつ重なりがないよう
にするのがおすすめです。
でも、それがちょっと難しいということもありますね。
たくさん着物や帯がある場合、干す場所が限られる場合など。
そんなときは、より簡単に虫干しできる方法を参考にしてみてください。
ロープや棒を使う簡単虫干し方法

◆部屋にロープや棒を渡してかける
たくさん着物や帯がある、あるいはスペースが狭いという場合は、部屋にロープをはって掛けるようにしましょう。
着物や帯をたたんだ状態で、床にふれないようにしてロープにかけます。
できるだけ高い位置にロープをはり、重なりが少なくするようにしてみてください。
簡単な虫干し・5つの方法
ロープや棒をはって干すということがむつかしい場合は、以下の5つの方法でやってみてください。
1・タンスの引き出しをあけて風を通す
タンスの引き出しを空けるだけでもある程度風を通せます。
たくさんの着物が重なっている場合は、上下を替えるなどしてまんべんなく風が通るように。
もちろん、最初の注意事項は守ってくださいね。
2・衣替えのタイミングで行う
虫干しだけのために年に三回もはとても。。。というときは、
衣替えのタイミングで年に二回を覚えておいてはどうでしょう。
- 夏物の着物に代わる6月の前に一回
- 単から袷に代わる10月の前に一回
3・着てお出かけして虫干し代わりに
すべての着物や帯を一度に虫干しするのは大変ですね。
それなら、一年で一回は着てお出かけするようにしてはどうでしょう。
もちろん季節にあった着物だけになりますが、そのときだけは着物の全体を点検するチャンスにもなります。
フォーマルな着物も、できるだけ機会を作ってみてください。
4・たとう紙に入れたまま虫干しする
吊るす作業が手間でできないというなら、たとう紙におさめた状態で室内に置きます。
着物を吊るしはしませんが、タンスの一段分を取り出して置くだけでも、随分と湿気はとばせます。
引き出しも出して、タンスの中の通気を良くすることもできます。
5・エアコンや除湿器の利用
湿気の気になる季節には、エアコンの除湿機能や除湿器の利用を。
着物の収納場所に除湿剤や防湿剤、または引き出しの下に除湿シートを敷いておくのも手です。
着物・帯の虫干しのときに合わせてやっておきたいこと
虫干しのときは、タンスやたとう紙にも目をかけてあげましょう。
- タンスの引き出しそのものを出して、ほこりをはらい乾燥させましょう。
- おさめてあるたとう紙の湿気も合わせてとるようにし、着物とセットで通気性のよいところに。
着物の虫干しの季節/時期はいつ?仕方と簡単なやり方5つの方法!NGは?まとめ
虫干しの時期は、乾燥した季節で晴天が2日以上続いたあとに。
もしカビを見つけたら、他の着物にカビが移るのをさけて、早めに専門家に。
上で紹介した5つの簡単な方法を参考に、ムリなくご自分にあった方法で。
<関連ページ紹介>
◆着物の収納保管どうしてる?桐ダンス以外の収納ケースは?
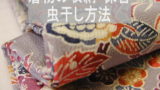
◆衣桁着物のかけ方・乱れ箱の使い方

◆帯揚げ・帯締めの手入れ・しまい方

◆お太鼓結びで結びやすい帯はどんな帯?





コメント