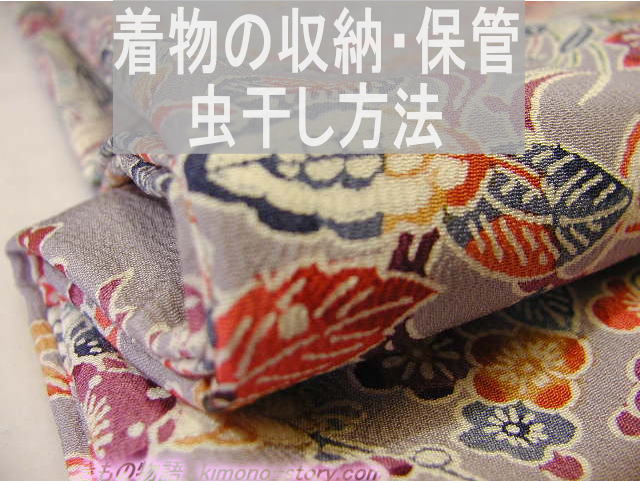
着物の収納といえば「桐ダンスが一番」といわれていますが、それ以外に洋服用の衣装ケースなどは使えるでしょうか。
着物にも、天然繊維ものからそうでないものまで種類があり、収納するにあたりコンパクトにまとめたいですね。
住宅事情、お持ちの着物の数なども関係すると思いますから、
あなたにとって「安全で安心、コンパクトな収納方法」を見つけてください。
ここでは着物の収納・保管について詳しくお話します。
- 桐箪笥が着物の収納に一番よいといわれるわけ
- 桐箪笥に代わる収納方法
- プラスチックケースに収納する場合の注意点
- 着物の虫干しの方法
- 防虫剤の必要性
では最初に桐箪笥の特徴をみてみましょう。
桐箪笥が着物の収納に一番よいといわれるわけ

「着物の収納は桐箪笥に決まっているわ」と着物の大先輩は言うでしょう。
その理由としては、桐箪笥は湿気を寄せ付けにくいという特徴があるからです。
着物は湿気が多いところでは、カビが生えやすくなり生地や染色を傷めてしまいます。
桐箪笥の素材の特徴
では湿気を寄せ付けにくい桐箪笥の特徴をまずみてみましょう。
湿度の調節機能がある
桐箪笥は、湿度が高くなると湿気を吸収して膨張し、湿度が低くなると湿気を放出して収縮します。
桐箪笥が雨の日に開けにくく、天気のよい乾燥した日にはすーっとあくのはそのためです。
湿気の多いときに膨張した桐箪笥は、箪笥の気密性を高めます。
そのため外気の湿気が入りにくくなり、中の着物に余分な湿気が含まれにくくなるわけです。
それで着物はカビの発生を予防できるというわけです。
逆に湿度が低くなると箪笥が収縮し、隙間ができます。
すると箪笥の中に、乾燥した空気が入り込み、箪笥内の湿度が低くなります。
そのため、カビの発生を防ぐことができるのです。
虫がつきにくく燃えにくい
桐箪笥は湿気の調節をしてくれること以外にも、桐自体が「虫が付きにくい」、「燃えにくい」という特性もあります。
虫がつかない・燃えにくい、どちらも大切なものを入れておくのに大事な要素ですよね。
このような理由で「着物は桐箪笥に」といわれるわけですね。
<桐箪笥が着物によい理由のまとめ>
- 湿度の調節機能がありカビを寄せつけにくい
- 虫が付きにくい
- 燃えにくい
桐箪笥のよさはわかりましたが、「桐箪笥はとても高価」という印象がありますね。
また「桐箪笥を置く場所がない」という住宅事情もありますね。
ではそんな場合はどうするとよいでしょう?
桐箪笥に代わる収納方法

桐箪笥でなくても、着物を保管することはできます。
プラスチックの衣装ケースやクローゼット(洋服ダンス)でも、保管できます。
ただ、それぞれちょっとした注意は忘れないようにしたいです。
プラスチックの衣装ケースに収納するときの注意点
「衣装ケース」は洋服でも利用し、使いかってがよくおなじみですね。
重ねることができ、収納力もあります。
プラスチックの衣装ケースに着物を収納するときに注意したいのは「湿気」です。
桐ダンスのように自動で湿度の調節ができないので、
とにかく湿気をとる(よせつけない)ようにして、カビなどのトラブルを防ぎましょう。
<衣装収納ケースに着物を保管するポイント>
- 除湿シートを入れる
- 着物を入れて余裕のある大きさで利用する
- 定期的に風を通す
着物をいれて余裕のある大きさのケースを
着物を入れるケースの大きさは、収納スペースとの関係で、ご自分にあった大きさを選びます。
- 着物を二つ折りにしたときの大きさ:縦 75~85cm×横 35~40cm
- 着物を三つ折りにしたときの大きさ:縦 55~65cm×横 35~40cm
たとうしに入れる場合も、ほぼ同じ大きさです。
プラスチックの収納ケースにはたくさんはいりますが、ウールの着物や帯は他の素材と別にまとめましょう。
おすすめの着物収納ケース
帯や小物までそろえてまとめておきたいときにおすすめの収納ケース。
クローゼットの上段に置いても取り出しやすい。
収納袋が5枚セットされ、防虫剤のポケット付きという使いやすさが魅力の収納ケース。
こちらも高いところに置いても取り出しやすい、というのが嬉しい。
たっぷりの着物をまとめるには、やはり大きな収納ケースがいいですよね。
これなら、三つ折りにして小物もまとめられそうです。
(引出内寸:約64.5cm×約36cm×約14.5cm プラスチックケースの場合は内寸を確認してね)
洋服ダンスに収納する場合の注意点

洋服ダンスで着物を収納することもできます。
ただ、プラスチック収納ケースと同じように、湿気がこもりやすいので湿気対策が必要です。
晴れた日や湿度がひくい日は、扉を少し開けておくとよいです。
そうすれば洋服ダンス内が換気され、湿気を出すことができます。
またつめ込みすぎないようにしましょう。
着物の湿気をとばす=虫干し

収納ケースに入れるにしても洋服ダンスにしまうにしても、時々は外に出して湿気をとばすようにしましょう。
湿度の低い晴れた日を選んで、年に3回が理想です。
湿気をとるのに適した時期
湿度が低い=乾燥した季節がよく、以下の時期です。
- 7月下旬~8月上旬
- 9月下旬~10月上旬
- 1月下旬~2月上旬
ケースから出して、一枚一枚を「吊るし干し」に。
これを「虫干し」といっていますが、着物を乾燥させることで害虫被害から守ります。
着物の虫干しの方法
虫干しは着物も帯も一枚一枚を広げて、着物ハンガーで吊るすのが理想的です。
(洋服のハンガーの場合は3~4時間の短時間で)
でも枚数が多い、スペース的に無理ということであれば、たたんだ状態で部屋にはったロープに掛けるなどでもよいでしょう。
そして以下のことを守って行ってくださいね!
<虫干し(着物を乾燥させる)ときの注意>
- 風通しのよい室内で
- 直射日光をあてないようにして
- 蛍光灯の光にもあてないようにして
- 午後4時頃までにはしまう
え?面倒そうですって?
それならできるだけ晴れた日に着物を着るようにするとよいですね(^o^)
湿気の少ない日に、着て外出することが虫干しの代わりになります。
吊るすのは結構大変なので、「収納ケースのふたを開けておく」だけでもやってみましょう。
保管・収納の仕方は同素材で

保管・収納の考え方
着物の保管・収納の考え方は、この二つが一般的です。
- 「季節ごとに分ける」
- 「用途によって分ける」
数が多くないなら、季節ごとに分けシーズン到来とともにすぐに利用できるようにするとよいですね。
そして生地の材質ごとに分けておくのも、よい方法だと思います。
材質の同じものは、保管収納する際の扱いが同じなので、防虫剤を入れる量、湿気を発散させるタイミングを同じくできるからです。
- 絹のものは絹同士
- 木綿のものは木綿同士
- ウールのものはウールのもの同士
- 洗える着物は洗える着物同士
たくさんお持ちなら帯も素材ごとにまとまっていた方が、着物とのコーディネートを考えるときに便利です。
そして上段ほど品質のよいものを入れて、少しでも湿気をさけるようにします。
箪笥も収納ケースも、下よりは上に、押し入れの下段よりは上段に、品質のよいものを保管するようにします。
虫の被害にあいやすい素材のウール

素材としてはウールの着物が虫の被害にあいやすいです。
ウールは虫のエサになり、卵を産み付やすいからです。
そのためウール着物や帯の保管には防虫剤をいれて保管するのがよいです。
ウール素材のものは一つにまとめて、防虫剤を有効に効かせましょう。
防虫剤の必要性について
絹の着物は、ほとんど虫食いの被害はありません。
でも絶対ではないですから、匂いのない防虫剤を使うとよいと思います。
使うのは必ず一種類だけにしておきます。
複数使うと、こんな困ったことが起こるからです。
- 衣類にシミができる
- 匂いがひどくなる
- 有害物質を発生する
天然成分由来の防虫剤で、無臭のものがなお安心です。
着物の収納保管どうしてる? 桐箪笥以外の衣装収納ケースおすすめは/湿気対策・まとめ
上質な着物は桐箪笥へ収納するのが望ましいものの、
湿気をためないようにすれば、プラスチックの収納ケースでもできます。
湿気をとるため、除湿シートや年2回以上の「虫干し」がおすすめ。
防虫剤は一種類だけにし、無臭のものがおすすめです。
天気の良い日に着物でお出かけすれば、虫干しの代わりに。
<関連ページ紹介>
◆帯揚げ帯締めのしまい方と手入れ・次に使う準備もかねて

◆腰ひもと伊達締めのしまい方・たたみ方・手入れと洗濯

◆着物の虫干しの季節・時期はいつ?仕方と簡単な5つの方法

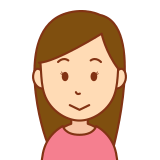
最近は、桐箪笥でキャスター付きでウォークインクローゼットに収納しやすいタイプのものが出ていますね。
プラスチックケースもキャスター付きなら、風通しのよい部屋へ移動させるのも簡単です。
ケースは必ず内側のサイズを確認してくださいね。
(きらこよしえ)







コメント