
節分ってどんな行事?
なぜ豆まきするの?
と子供に聞かれたときに、さっと答えられるよう心づもりしておきたいパパママへ。
どんな行事なの?の質問には。
「幸せを呼んで健康を願う行事だよ」と。
そしてなぜ豆まきするの?の質問には、
「わざわいをもたらす者(鬼)を豆(魔滅)で追い払うために「豆まき」をするよ」と。
。。。これで納得してくれたらよいのですが、子供はさらにこう聞いてくるかも。
「豆まきってどうやってやるの?」
「巻きずしを食べるのはなぜ?」
そんなときのために
- 節分の豆まきのやり方
- 豆まきの豆は大豆?それとも落花生?
- 節分のとき「恵方巻き」を食べるのはなぜ?
についてもまとめています。
2023年(令和5)の節分は2月3日(金)。
節分(豆まき)の由来

節分にどうして豆をまくのか?
豆まきを一言でまとめると、
つまり悪さをする鬼を豆で追い払うわけです。
子供向けに節分(豆まき)の由来・まとめると
- 節分(豆まき)は、怖い出来事や病気を追い払って幸せを呼び込む行事
- 怖い出来事や病気が「鬼」
- 鬼の嫌いな豆で鬼をやっつけちゃおう
節分(豆まき)のいわれを詳しく

次は、理解しやすいよう詳しくみてみましょう。
「節分」は季節を分けるとかき、季節が移り変わる節目を指しています。
立春・立夏・立秋・立冬のそれぞれの前日に、1年に4回あるのが節分です。
日本では立春は1年のはじまりとしてとくに尊ばれていたので、
しだいに節分といえば春の節分のみを指すようになっていきます。
難を追いやる・起源は宮中行事
昔、季節の変わり目には「邪気が入りやすい」と考えられていました。
その邪気を払って福を呼び込むために、
宮中で追儺(ついな・難をおいやる)の行事が行われていました。
室町時代以降になると、豆をまいて邪気(鬼)を追い出す行事へと発展していきます。
それがしだいに民間にも定着していったという経緯です。
「鬼が邪気」というのはどうして?
鬼を邪気として追い払うのは、鬼(おに)が「陰(おん)」に由来していて、
陰(おん)は目に見えない邪気を指しているためとされています。
また鬼は「隠人(おんにん)」が変化したものだという説も有力です。
隠人(おんにん)は隠れた不運な出来事つまり、
自然災害や飢饉、流行病など人の力ではどうすることもできない不幸のことです。
不幸は鬼のしわざだと考えられていたためです。
「邪気そのものである鬼を退治し、福を家に呼び込みたい」
そうした願いを込めたものが「豆まき」です。
豆まきのやり方・いつやる?

ではその豆まきのやり方ですが、これは各家庭に伝わるやり方でかまいません。
といっても自分が子供の頃のことなんて思い出せない。。。
豆まきのやり方・2月3日の夜
最低これだけはというやり方は、
- 家族がそろった夜に豆まきをする
- 窓を全部開けて「鬼は外!」窓を閉めてから「福は内!」という
- 豆を全部ひろってから、歳の数だけ食べる
鬼は外、福は内、どちらを先に?

きちんと豆まきをやりたい、という人は、こんな流れで行うのがおすすめです。
鬼(邪気)は夜中にやってくるとされていますから、夕食後に家族がみなそろってから一斉に豆まきをします。
<家中から鬼(邪気)を追い払う豆まきのやり方>
- まず家中の窓と玄関を開ける
- 家の主が玄関から遠い方の窓から大きな声で、窓ひとつずつに向かって「鬼は外!」と言っては豆をまく
- 窓全部にまいたら、最後に玄関に向かって「鬼は外!」といって豆をまく
- そしてすぐに窓と玄関を閉める
- そのあとすぐに「福は内!」といって奥から順に玄関まで「福は内!」といって部屋に豆をまく
豆まきが済んだら、無病息災を願って歳の数だけ豆を食べます。
歳の数え方は満年齢・数え年とありますが、今は満年齢が一般的。
鬼を外へ追いやってから、福は内にとどまるようにということですね。
豆まきの豆は大豆?それとも落花生?

◆炒った大豆
豆まきに使う豆を「福豆」と呼びます。
節分の豆まきに使う豆は、
- 関東以北では落花生が主流
- 関東以南は大豆が主流

◆落花生
落花生なら豆が汚れず、拾い集めやすいです。
保育園や小学校で行われるときは落花生をまくことが多いようですね。
※落花生は殻を一つと数えます。
大豆は生でなく炒った豆を使います。
<炒った豆を使う理由>
豆が生だと芽が出でしまうことがあり、「芽が出るのは縁起が悪い」とされているためです。
また「炒る」は「射る」にも通じ、悪魔の目を射ることで「魔を滅する」(魔滅)ことができるからともいわれます。
節分のとき恵方巻きを食べるのはなぜ?

さて、節分のときの食事といえば「恵方巻」ですが、まずは子供向けには、
恵方巻を食べる・子供向けにまとめると
子供向けにざっくりまとめて伝えるとすると、
- 幸運や金運を司る神様のいる方角に向かって願い事をすると叶うといわれているよ
令和5年2024年の恵方は?
「恵方」とは「縁起のいい方角」のことです。
恵方とはその年に「歳徳神(としとくじん)という神様」がおられる方角で、
この神様は幸運や金運を司る神様で、毎年居場所を変えるとされていますよ。
令和6年 2024年2月3日(土)は「東北東」です。
恵方巻の由来・いわれ

「恵方巻き」というのは、節分の日に恵方を向いてだまって一本丸かぶりする太巻き寿司です。
恵方巻を食べると縁起がよいとされ、定着していますね。
以前は節分(豆まき)の日に特別な食事をする習わしはありませんでした。
恵方巻きを食べるようになったのは諸説ありますが、
- 大阪で節分の日に巻きずしを食べる習慣が以前よりあったこと(大正時代)
- 大阪の海苔業界が戦前に「恵方巻を食べると幸運に恵まれる」としたチラシがあること
- 1970年代コンビニ業界などの関係業界が主導して、海苔の販売促進を狙って宣伝を大々的に行ってきたこと
- 1980年代に別のコンビニでも宣伝を行うようになり、全国にひろまるきっかけとなった
というような時代の流れがあります。
節分に豆まき なぜ?落花生か大豆どっち?やり方/子供に伝える2024年2月3日・まとめ
節分は豆をまき鬼(邪気)を追い払い、無病息災と幸せを願う行事。
恵方の神様は幸運と金運の神様。
恵方巻の食べ方は恵方に向かい黙っていただく。
「丸かぶり寿司」、「幸運の太巻寿司」などの名称も耳にしますね。
ご家族皆さまのご健康・ご多幸をお祈りいたします。
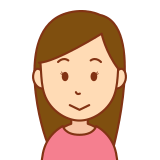
そんなことを心配していたら。。。
なんと鬼を改心してくれるところがありました!
鬼たちは改心させられた後に、「福の神」となってまた全国に送り出される!」そうなのです。
よかったよかった。
追いやられた鬼を歓迎してくれるのは、奈良県吉野町の「金峯山寺(きんぷせんじ)」。
ここでは、「福は内、鬼も内」 と唱える鬼の調伏式が行われます。
とっても珍しい節分会の行事ですね。
火の祭典とともに、金峯山寺本堂蔵王堂で盛大に営まれています(毎年2月3日・年により変更することあり)
<関連ページ紹介>
◆ひな祭りの由来・雛飾りはいつからいつまで?

◆ひな祭りの食べ物・ちらし寿司とはまぐり







コメント