
浴衣や木綿の着物は、シワになりやすいのが気がかりです。
放っておけないシワには、やはりアイロンがけが必要ですね。
着物は面積が大きいのでアイロンをかけにくいですが、このコツを身につければ大丈夫。
「ひと工夫」と「プロ直伝の順序」で行えば、シワを伸ばすのも楽になりますよ。
- 浴衣・木綿きもののアイロンがけのコツ
- 干すときのひと手間
- アイロンをかけるときの順番
- アイロンがけのときの注意
- シワがのびやすいのはスチーム?霧吹き?
この順に詳しくお話しますね。
浴衣・木綿きものアイロンがけのコツと基本

シワしわの浴衣も、アイロンがけのコツさえわかればきれいにシワなしにすることができます。
アイロンをかけるときのコツ、それは力の入れ方です。
絹の着物のときは力を入れませんが、木綿のときは力を入れます。
これからお伝えする「アイロンがけの基本」をおさえてくださいね!
<木綿着物のアイロンがけの基本>
- アイロンの後ろの方に力を入れて、とがった先をわずかに浮かす
こうすると生地と接する部分が後方だけなので、スイスイっと自然に滑っていきます。
干すときのひと手間でアイロンを減らす
力を入れてアイロンをかけるのは、結構大変。
だから極力減らしたい。
そのためには、干すときにこんなひと手間をしてみてください。
以下三つ紹介しますね。
干すときのひと手間1・バンバンっとはらう
これ、洋服を干すときにもやっているかもしれないですね。
干すときに、2~3度はらうっていう動作。
木綿の服やタオルなど、干すときに上の端を持ってバンバンっと2~3度はらうと思います。
それを浴衣(木綿の着物)のときもやるわけです。
こうしておくとシワをある程度のばしておくことができます。
干すときのひと手間2・引っ張る
着物ハンガーに干すとき、生地を引っ張りましょう。
- 袖を縦方向に引っ張る
- 身頃も縦方向に引っ張る
- 衿も同じように衿先を引っ張る
これで洗いあがりのシワが減ります。
引っ張るときは、片手でなく両手で引っ張り合うようにします。
干すときのひと手間3・手で挟む
また細かな洗いジワをとるには、手で挟むのも効果があります。
具体的には、両掌で生地を挟んで、押し付け合うようにしてすべらせます。
またパンパンっとやはり両掌で挟んで、シワのところをたたきます。
こうすると後からのアイロンがけが楽になりますよ。
※干すときの型崩れを防ぐ着物ハンガー
浴衣・木綿着物のアイロンのかけ方

◆浴衣 アイロン 霧吹き
では実際に浴衣(木綿の着物)にアイロンをかけましょう!
アイロン台の上にのせたら、かけるところの形を手で整えてからかけるようにします。
シワのあるところに霧吹きで霧をかけて、その都度アイロンをかけます。
アイロンをかける順番
新たなシワをつけたくないので、アイロンをかけるときはこの順で行うのがおすすめです。
<木綿きものにアイロンをかける順番>
- 最初に袖と衿に
- 身頃の裏を向け、後ろ身頃の繰り越し(肩山から40センチほどのところにある縫い目)より上に
- 表側にして前身頃と後ろ身頃を重ねて、前身頃側から
その後は本だたみするときのようにたたみながら、アイロンをかけます。
↓↓つづき
- 左側が肩右側を裾にして、手前にある右の脇線を折りたたんで、前身頃の上から
- 裾から肩山まで
- おくみを折り返して、向こうにある上前のおくみ・衿を重ね、おくみのところに
- 向こう側の左の脇を手前にある右の脇に合わせて、背縫いがまっすぐになるように整え、裾から肩山まで
- 左袖・右袖を外側に折り、右の後身頃が出るようにし、右の後ろ身頃にシワがあればアイロンをかけて終了
アイロンをかける時の注意点
以下のことに注意してかければ、さらに効率的です。
<アイロンをかけるときの注意点>
- アイロンをかける前に手で必ず生地を平たくしておく
- アイロンの後方に力を入れ、アイロンの進む先の生地をもう一方の手で軽く引っ張りながら
- 広い台で着物がのるくらいの長さがあるものがやりやすい
- 大きな台がない場合は、床に薄い毛布か平なバスタオルを敷きてかけてもよい
- 「きせ」はつぶさないように
ビシっと仕上げたいときは、スプレー式のアイロン用のり剤を使ってくださいね!
シワがのびやすいのはスチームそれとも霧吹き?

シワが取れやすいように、スチームまたは霧吹きを使います。
スチームか霧吹きか、どっちがシワがとれるでしょう。。。
答えは。。。木綿の着物のシワとりは、霧吹きを使う方が断然よくとれます。
理由は霧吹きの方が、スチームより繊維に水分が残りやすいからです。
「スチームの水滴の大きさは、霧吹きの水滴の大きさのなんと100万分の一!」
しゅーっと吹きかけてもほとんどが繊維を通り越してしまい、繊維に水分を残さないのです。
勢いよく出るスチームですが、数回のスチームより一回の霧吹きの方が、繊維に残る水分量が多くシワが取れやすいです。
ですからぜひ霧吹きを使ってくださいね。
シワののびる仕組み
余談ですが、シワがのびる仕組みについても少し。
木綿の繊維に水が入ると、シワという分子の結合状態が解けて分子が自由に動けるようになります。そこにアイロンをかけることで分子が整然と並んで、乾くとその状態が固定され、シワがなくなるという仕組みです。
木綿と麻は水に濡れやすいため、霧吹きなら十分に繊維の中まで濡れるので、シワがとれやすいのです。
浴衣や木綿の着物のシワの伸ばし方/プロ直伝/アイロンがけの順序とコツまとめ
浴衣・木綿の着物へのアイロンがけは、干す段階でひとてまかけておくと楽になります。
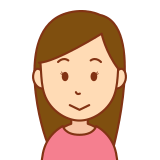
洗ったあとの脱水時間が長いとシワができやすいので、ゆるめに脱水してください。
あと少しで乾くときに(湿気が少し残っている状態)で取りこめば、そのままアイロンをかけていけます。
<関連ページ紹介>
◆絹の着物のシワ取り、しわ伸ばし・アイロンをかける具体的な方法

◆麻の帯のシワをとる方法・アイロンのあて方とおすすめの寝押し

◆長じゅばんのシワをとりたい・アイロンのかけ方・正絹のしわとり






コメント