袋帯で結ぶ「立て矢結び」の結び方を詳しく解説します。
「お太鼓結び」「文庫結び」と並んで帯結びの基本形のひとつです。
「立て矢」は若々しさと、きりりとした華やかさが印象的。
花嫁のお色直しの帯結びに用いられることが多いようです。
江戸時代の大奥の御殿女中が結んでいた結びでもあります。
テレビドラマの大正時代の設定のとき、若い女性が立て矢を結んでいることがあります。
立て矢結びの特徴
立て矢結びは、その名の通り、背中に矢が立っているような形状をしています。
帯の一部が直立し、矢じりのように尖った形になるのが特徴です。
この結び方は非常に複雑で洗練されており、豪華な振袖と合わせることで、華やかな装いを演出します。
立て矢(袋帯)の結び方/やり方手順

◆立て矢結び
基本の「立て矢結び」です。
左上から右下に向かう形で、背の高い方に向いているでしょう。
羽根の形を変化させることで、さまざまな立て矢のアレンジ結びがあります。
では最も基本形の立て矢の結び方を、手順をおって紹介します。
基本形・手先を上にしてひと結び

手先を60センチほどとって、胴にぴったりと二巻きします。
手先を上にあげてひと結びします。
手先を仮りひもでおさえる

手先を三分の一幅にして、紐で押さえます。
この紐はあとでとります。
長さ50センチの羽根をつくる

たれの元をしっかりと開いてから、
たれの先が内側に入るようにたたみます。
長さ50センチくらいの羽根を作ります。
箱ひだをとりゴムでとめる

羽根に箱ひだをとります。
形が動かないように中心をゴムで留めます。
帯揚げをかけた枕をおく

羽根の左上が肩から少し出る位置にきめます。
帯揚げをかけた帯枕を羽根の中心付近にあてて、枕の紐を前で結びます。
帯揚げはあとで飾るので軽くとめておきます。
帯締めをしめる

手先をおろして帯締めをとおします。
帯締はしっかりと締めます。
箱ひだの形を整えて、立て矢結びの完成です。
立て矢結びのポイント
「立て矢結び」の羽根は、正面から見て左肩に少し見えるくらいの大きさがよいです。
左上方向と右下方向の羽根の大きさ(長さ)は、同じが基本です。
立て矢のアレンジ帯結び

◆袋帯 立て矢結び アレンジ
アレンジについては、羽根の形を様々に変えることでアレンジします。
現代では基本の形で結ばれることはほとんどなく、アレンジをした豪華な印象の結びが主流です。
立て矢結びの歴史
立て矢結びは、日本の伝統的な帯結びの一つで、特に振袖に合わせて用いられることが多い装いです。
立て矢結びの正確な起源については、詳細な記録が残っていないため、具体的な時期を特定するのは難しいですが、以下のような歴史的背景が考えられます。
立て矢結びは、おそらく江戸時代(1603年〜1868年)に発展したと考えられています。
この時代には、着物や帯結びのスタイルが非常に発展し、多様な結び方が生み出されました。
特に、舞妓や芸者などの伝統的な日本の芸能人が、その華やかな衣装として立て矢結びを用いることがありました。
豪華さと目立つスタイルのため、特別なイベントや祝い事での装いとして好まれることが多かったとされます。
現代では、立て矢結びは成人式や結婚式など、特にフォーマルな場面で未婚女性が着る振袖と合わせて用いられます。
この結び方は、伝統的な日本の美しさを象徴すると同時に、着用者の華やかさと若々しさを際立たせる効果があります。
立て矢結びのような伝統的な帯結びは、日本の文化として大切にされており、特別な日の装いとして今もなお親しまれています。
袋帯 立て矢結び 結び方/やり方/基本形を詳しく解説・まとめ
「立て矢」結びは「お太鼓」「文庫」とならんで袋帯の結びの基本です。
「立て矢」結びは江戸時代からあり、現代でも花嫁のお色直しに結ぶことがあります。
左上から右下に向かう形が特徴で、背の高い方に向いています。
基本形をさまざまにアレンジした変わり結びがあります。
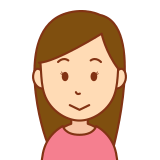
基本の「立て矢」結びは、時代物のテレビドラマで時々見かけます。
NHKの朝ドラの「ごちそうさん」(2013年度下半期)でお見合いのとき、杏さんが振袖にこの立て矢を結んでいました。
18歳くらいの想定で、昭和始めころの時代設定でしたよ。
当時は袋帯でなく「丸帯」でしたから、豪華な織り模様が見事でした。
(きらこ よしえ)
<関連ページ紹介>
◆袋帯で文庫結びの結び方・詳しく解説・清楚な振り袖の装いに

◆ふくら雀の結び方を詳しく解説・伝統と格式のある帯結び

◆袋帯の部位の名称・かいきり線とオランダ線・仕立て方による違い






コメント