
◆ジャカード織りの生地のワンピース
着物・和装で語られるジャカードとは、
織物の経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を複雑に組み合わせて、
模様を織り出した織物(紋織物)の機械技術を完成させた、
フランス人、ジョセフ・マリー・ジャカードのこと。
また、紋織物の織機のことをいいます。
ジャカードを英語読みすると
ジャカードは英語表記で「Jacquard」。
カタカナ読みで「ジャカード」となります。
しかし、日本では「ジャガード」の方がよみやすいことで一般的となり、濁音読みの「ジャガード」が使われるようになりました。
ジャカード織物の仕組み
ジャカード織機は、紋紙(もんがみ)と呼ばれる穴をあけたカードを利用して、
経糸を上下させて、緯糸が通る個所を変えることで、模様をつくりだしていきます。
実際に布を折り始めるまでには、
まずどんな模様にするのかを決め、図案におこします。
図案には出来上がりの色や、経糸緯糸の使い方によって、
色を塗り分けていきます。
それをもとに、紋紙(=穴をあけたカード)を作っていきます。
ジャカード織機によって、経糸の制御ができることになり、
それまで経糸の操作のため織機の上にのっていた人は。必要なくなりました。
織リ手は二人でなくひとりで済むようになり、
作業効率があがることになりました。
ジャカード織りが用いられる製品

◆ジャカード織りの生地のトップス
ジャカード織りは、その複雑な模様とデザインのために高級品や特別な製品によく使われます。
ジャカード織りの技術を採用した製品としては以下のようなものがあります。
- ファッションアイテム: ドレス、スカート、ジャケット、ネクタイなど。
- ホームデコレーション: クッションカバーやカーテン、ベッドリネンなど。
- アクセサリー: バッグ、財布、ショールなど。
紋織物の歴史
中国からシルクロードを通って、
15世紀にヨーロッパに伝わった紋織物。
フランスのリヨンで技術の研鑽が行われ、
ジャカード織機の元になりました。
紋織物の発展は、順調とばかりはいえなかったものの、
皇帝ナポレオン・ボバパルトが絹織物の大量発注をすることで、
絹織物産業が急成長し、以降発展を遂げていきました。
皇帝ナポレオンが、ジャカードの織機とリヨンの博覧会で出会い、
報酬を与えて保護していくことで、
ジャカードの名は広く浸透していくことになります。
ジャカード装置が普及するにつれて、
紋織物の量産が進んで、多くの人の手に渡るようになっていきます。
シグネチャ―ジャカードって何?
バッグの生地などに使われるシグネチャー ジャカードという素材は、
再生ポリエステル繊維と、化学肥料や農薬を使わない認証オーガニック コットンの混紡で作られています。
<関連ページ紹介>
◆紋織物とは・意味や歴史・西陣の紋織物・機械織りのジャカードの技術

◆着物を着てどこへ行ったらいい?きものでお出かけしたいけど。初心者中級者

◆木綿の着物・合わせる帯と着る季節は?特色ある木綿着物



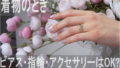

コメント