
居敷当て(いしきあて)は、着物のヒップの生地や縫い目を保護するために当てる生地です。
着物での立ち座りの動作で、ヒップ付近には大きな力がかかります。
そのため生地や糸に負担がかかり、弱りやすいです。
そこであらかじめ別の布=「居敷当て」を裏側に取り付けておき、着物の傷みを防ぎます。
居敷当てをつけるのは、通常浴衣や普段用の着物につけます。
では、ついていない着物に居敷当てをつけてみましょう。
作り方とともに詳しく説明しますね。
居敷当てに適した布と着物
最初に、居敷当てに適した布を紹介します。
それは、きものより薄い生地で木綿の薄手の白生地が適しています。
着用したときに表側への影響がないなら、色がついていても構わないでしょう。
ウールや木綿の着物には、着物の余り布(共布)を取り付けてもよいです。
居敷当てをつける着物の種類
取り付ける着物は、
- 頻繁に着る普段用の着物
- 浴衣
- 夏用の透ける着物
主に裏地のない着物に取り付けます。
<居敷当てを付ける着物の種類>
- ひとえの絹きもの
- 木綿きもの
- 麻きもの
- ウールきもの
- 浴衣(ゆかた)
またよく着る長じゅばんに取り付けることもあります。
いずれにしても、着物のヒップの生地や縫い目を保護したいとき、すけるのを防ぎたいときです。
ここで紹介するのは着物の保護が目的の居敷当て
では居敷当てを取り付ける方法を詳しくお話します。
ここで紹介するのは、着物のヒップの生地や縫い目を保護目的で、普段用~おしゃれ用の着物にとりつける居敷当てです。
※透けるのを予防するためのものではありません。
居敷当てに向く生地と大きさ(サイズ)

◆新モス
居敷当てに使う生地は、丈夫な木綿生地が向いています。
ここでは「新モス」と呼ばれる綿100%の生地を使用しました。
「新モス」は晒(さらし)より生地の目が細かい薄手の生地です。
新モスにはカラーもあります。

◆新モスのラベル
「新モス」は幅約35センチ、長さ約21メートル。
10メートルくらいの長さのものもあります。
<いしきあて・出来上がりサイズ>
- たて40センチ、横33センチ
※幅はミミなのでそのまま、上下の縫い代がそれぞれ2センチ必要
居敷当ての作り方
作り方は次の5つのステップです。
- まず縫い代分の長さを含めて布を断つ
- 軽く水洗いしてアイロンをあてる(縮み防止のため)
- 布のミミになっているところは1センチ折り曲げ、断ち切ったところは1センチの三つ折りに
- 上の左右の角はアイロンで少し折る
- 下端は三つ折りにして縫う
居敷当ての取り付け位置はどこ?
次に取り付け位置を確認します。
居敷当ての上端が腰骨のあたり、そして下端がひざ上10センチのところが取り付け位置です。
目印になるよう糸印をつけるなどしておきます。
居敷当て取り付け開始
まず着物の裏を出して始めます。
この例はシルクウールの紫色の着物です。
ステップ1・中央を着物の背縫いに取り付け

◆背中心に取り付け
最初に「いしきあて」の中央を着物の背縫いに取り付けます。
背中心の縫い代の1~2ミリ右にして、「いしきあて」待ち針で留めます。
そこを上から下まで縫います。

◆居敷当て・下端中央
居敷当ての下端の中央のところです。
取り付ける際の縫い始めと終わりは、しっかりと取り付けてください。
ステップ2・居敷当ての周囲を縫い留める
次に居敷当ての周囲を縫い留めます。
表生地には1~2ミリの針目がでるくらいの、小さい針目にします。
参照・角と下

◆居敷当て・右上の角のところ
居敷当ての右上の角のところの様子です。

◆右下の角のところ
居敷あての右下の角のところの様子です。
以上で取り付けができました。
縫いにくい場合はこの方法でも
居敷当ての表側に糸が見えないように縫う方法を紹介しましたが、
縫いにくいということであれば、糸が居敷当て側に出るように縫ってもいいでしょう。

◆居敷当て側に縫い糸を出して縫ってもうよい
左側部分を、糸が出るように縫いました。

◆左上角と左の上部、糸を出して縫う
左上の角のところと左の上部も、糸を出す縫い方で縫い付け方ました。
居敷当て取り付け完了

◆居敷当て取り付け完了
居敷当ての取り付けができました。
いしきあて 居敷当て の作り方 付け方/後付けの手順を詳しく解説します・まとめ
居敷当ては着物のヒップの生地や縫い目を保護するもの。
着物より薄い生地で、木綿の薄手の白生地がおすすめ。
上部の角が折ってあるのは、折ってとりつけるとおさまりがよいからです。
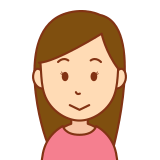
居敷当てがあると、着物のヒップのカーブが付きにくいのもよい点です。
特に麻の着物には取り付けをおすすめします。
(きらこ よしえ)
<関連ページ紹介>
◆袋名古屋帯のほつれを自分で直す

◆ひとえの着物の裾直し・詳しく解説

◆かんぬき止めのやり方・手縫い詳しく

◆身幅のお直し方法・許容範囲・着こなしでのりこえるには





コメント