
前だけの帯って知ってますか?
後ろに結びめやお太鼓がないんです。
「なんちゃって帯」または「簡易帯」とよばれる帯について、お伝えします。
この帯は、前から見ると帯をちゃんと締めている姿に見えます。
ですが、後ろから見ると「あれ?」ということになります。
つまり後ろの帯結びがないのです。
なので帯を締めているようにみせているだけ、なのですね。
- なんちゃって帯(簡易帯)の例
- 特徴
- 外出の際に気をつけたいこと
- 現代のなんちゃって帯(簡易帯)と着装例
順をおってお話しますね。
※帯結びがある「作り帯」とは別のものです。
昭和の「なんちゃって帯」

◆なんちゃって帯・簡易帯の例(昭和初期)
この「なんちゃって帯」は、昭和10年前後のころのものと思います。
胴に巻く帯の端に、短い帯締めが二本ついています。
特徴・素早く身に着けられる
身に着け方は、胴に一重巻きつけ、帯締めを前にもってきて結びます。
それで完成。
この帯は染めの帯地で、名古屋帯の帯地のようにみえます。
裏側にも模様があり、芯がはいっています。
そのため両面を利用できます。
これをつけていると、お太鼓結びをしているように人からは見えるのです。
「なんちゃって帯」の後ろ姿は?
ばっちり!な前姿ですが、後ろ姿はというと。。。
お太鼓がないので背中はぺたんこです。
ですから外出のときは利用しません。
家の中にいるときだけの「簡易帯」ということですね。
外出時でも、羽織やコートを着ていれば、さして違和感はないでしょう。
着物姿をよく知る人にとっては、「あれ?お太鼓がない!」っというのが分かりますけどね。
体が楽、だからこんなときに利用も
つまり帯なのに締めなくていいので体が楽です。
家庭着として使うだけでなく、外出時でも活躍しますよ。
どんなときかというと、
- 車の運転をするとき
- 旅行などで長時間乗り物に座るとき
背もたれのある椅子に座るとき、背中に飾る結びがないので洋服と同じ感覚です。
外出の際の注意点
外出の際は、後ろ姿がぺったんこなのは「あれ?」という印象で貧相な感じになります。
それで問題ないわという人は、お出かけの際は、羽織(またはコート)を身につけて出かけましょう。
きちんとした着物姿になるために、胴帯と同じ生地(または模様)の「帯揚げ・帯締め・帯枕・お太鼓部分」を持っていきましょう。
そのためには、いわゆる作り帯のお太鼓が別になったタイプのものを、前帯につけて利用するのがいいですね。
なんちゃって帯(簡易帯)の例・現代版
現代の「なんちゃって帯」の例も紹介します。

◆近年のなんちゃって帯
これは、前30センチほどに薄い板がいれてあり、両端の金具に帯締めがつけてあります。
帯締めの色が微妙に違い、帯締めをちゃんとしているようにみえます。
帯板まで省略できるタイプなのでとっても便利です。
身に着けてみると、

◆なんちゃって帯を着物に装着
つけてみるとこの前姿に。
帯揚げがないことは、あまり気になりませんね。
なんちゃって帯(簡易帯)の作り方
ゼロから作るのは大変なので、切って加工してもいい帯で作ってみてはいかがでしょう。
胴に二重に巻く必要はないので、一重めは必要なく、脇の見えない位置から帯締めをつなげればできますね。
とっても簡単にできそうですね。
切ってもいい帯、きってもいい帯締めがあれば作れます。
前だけの帯/なんちゃって帯/簡易帯・締めないのでラク/外出時注意・まとめ
なんちゃって帯(簡易帯)は、普段の着物生活に便利。
帯締めがあるので、前からみればお太鼓をしている姿に見えます。
外出先では羽織ものをすることで、お太鼓がないことがわかりにくいです。
羽織を脱ぐことがあれば、必ずお太鼓部分や帯枕などを持ってお出かけください。
<関連ページ紹介>
◆作り帯、付け帯とは、名古屋帯を加工した例・市販品の例で詳しく解説

◆三分割の作り帯・作り方と装い方・手順付き

◆名古屋帯の作り帯・お太鼓の付け帯・固定型・身につけ方



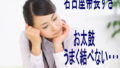

コメント